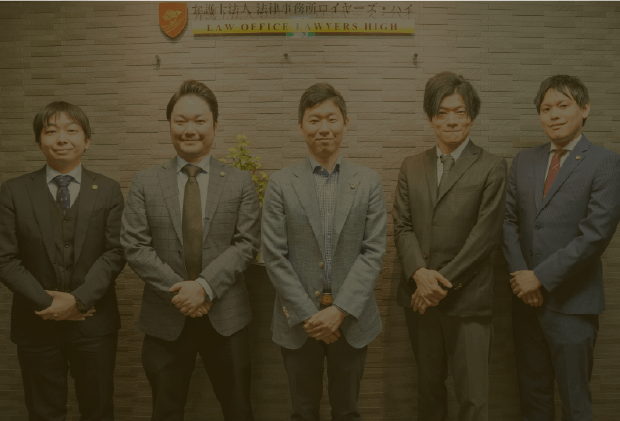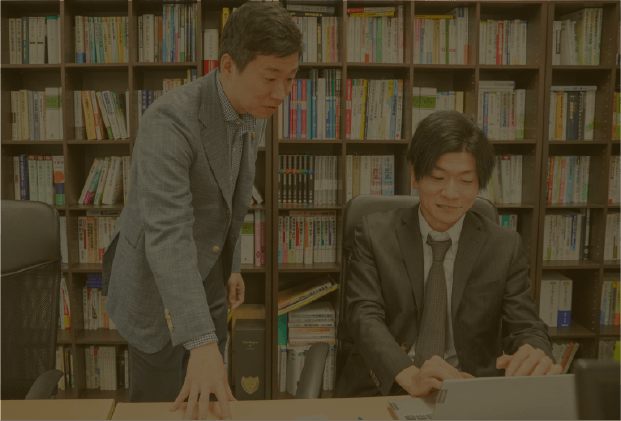交通事故において、加害者や加害者の加入する任意保険会社に誠実な対応をしてもらえない被害者の方は多くいらっしゃいます。加害者が保険に入っておらず、お金がなく、損害賠償を支払ってもらえない場合や、加害者の任意保険会社から過失の割合が被害者側にも大きくあるとして支払ってもらえない場合等様々な理由があります。
そうした時に被害者の方は泣き寝入りをする必要はありません。加害者が自賠責保険に加入している場合、被害者は自賠責保険に損害賠償の請求をすることができます。
ここでは、被害者が自身で手続きを行い、賠償金を受け取ることができる、「被害者請求」について説明をさせていただきます。
目次
交通事故の被害者請求とは?
a 自賠責保険とは
自賠責保険とは、交通事故において、被害者救済を目的とした保険です。自動車損害賠償保障法により、すべての車の所有者に加入が義務付けられており、加入していない場合は、車検は通らず、一般道を走ることはできません。
なお、自賠責保険は被害者の身体の補償に限られており、物損は補償対象ではありません。
自賠責保険への請求方法には【被害者請求】と【加害者請求】の2通りあります。
・被害者請求
交通事故の被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社へ直接保険金を請求する方法です。
・加害者請求
加害者が被害者の損が賠償金を支払った後に、保険金を自賠責保険会社へ請求します。加害者が任意保険会社に加入している場合は、任意保険会社がこの手続きを行います。
b 被害者請求の仮渡金請求と本請求
被害者請求には仮渡金請求と本請求があります。
・仮渡金請求
被害者は損害賠償金をすぐに受け取れるわけではありません。基本的には、示談が成立して損害賠償金が受け取ることができます。万が一裁判になった場合は、判決が出るまで受け取ることができません。
しかし、事故の影響で被害者は受け取るまでに治療費など予想以上に出費が重なることがあります。その結果、生活が圧迫する被害者も少なくありません。自賠責保険ではそういった被害者のために、【仮渡金制度】を設けています。これは、損害賠償額が確定する前に、必要なお金を請求できるという制度です。損害賠償金が確定したのちに清算となります。
・本請求
被害者の怪我が完治ないしは、症状固定により終了し、すべての損害が確定した段階で請求することをいいます。加害者と示談が成立していなくても、請求可能ですが、すでに加害者から損害賠償を受けている場合は、その分は差し引かれて、被害者に支払われます。
c 被害者請求でもらえる金額
自賠責保険へ被害者請求をした場合、以下の損害を請求することが可能です。
・傷害による損害
支払い限度額は1人最大120万円までとされています。ここには治療関係費用、文書料、休業損害、入通院慰謝料が含まれます。
・後遺障害による損害
被害者に後遺障害が残り、後遺障害等級(14級から1級)の認定が下りた場合、1人あたり75万円~4,000万円が支払われます。これは認定された等級によって金額が変わります。ここに含まれているのは、被害者が後遺障害により得ることができなくなった収入の減少(逸失利益)と後遺障害の慰謝料となります。
・死亡による損害
死亡事故の場合、1人あたり3,000万円が限度額とされています。ここには、葬儀費用の他、被害者と被害者遺族への慰謝料、死亡したことにより被害者が得ることができなかった利益(逸失利益)が含まれます。
被害者請求の手続きはどうすればいい?
被害者請求をするタイミングは、本請求か仮渡金請求かで異なりますが、方法は同じです。
被害者は、まず加害者の自賠責保険会社を特定します。加害者の自賠責保険会社は、自動車安全運転センターで発行される交通事故証明書に記載があります。保険会社がわかれば、そこへ連絡をすると、請求書類セットを送ってくれます。請求する内容に必要な書類を集め、書類がそろい次第、相手の加入している自賠責保険会社へ送り、直接請求します。
以下が必要な書類となります。
・自動車損害賠償責任保険支払請求書
申込書になります。被害者や加害者の基本情報(氏名や住所等)や受取口座を記載します。
・交通事故証明書
各都道府県にある自動車安全運転センターで発行される事故があったことを証明する書面です。加害者が任意保険会社に入っている場合はコピーをもらうことできます。被害者が用意する場合は原本が必要となります。
・事故発生状況報告書
交通事故証明書には基本情報しか記されておりませんので、どういった道路状況か、車の位置やスピード等詳しい事故状況を記す書面です。
・診断書・診療報酬明細書
交通事故の治療を行った医療機関にて医師からもらいます。複数の病院に通院をした場合は、全病院分が必要となります。
・施術証明書
整骨院や接骨院での施術を受けた際に必要となる書類です。
・印鑑証明書
請求者である被害者の印鑑証明書が必要となります。各市区町村役場で発行をします。
・後遺障害診断書
後遺障害の等級申請を行う際に必要となります。主治医が作成するものとなり、通常の診断書とは別の書式となります。
・レントゲン写真やMRIなどの画像
後遺障害診断書と同じく、後遺障害の等級申請を行う際に必要となります。
・休業損害証明書
交通事故の怪我により、収入が減少した場合、それは被害者の損害となります。この書面は勤務先に作成してもらう書面となり、事故の前年度の源泉徴収票や賃金台帳の写し、所得証明書のいずれかが必要となります。
・通院交通費証明書
通院時にかかったタクシー代や公共機関の費用を請求するための書類です。自家用車で通院をした場合も、自賠責基準で計算されたガソリン代が支払われます。
・委任状、委任者の印鑑登録証明書
もし、弁護士など第三者が被害者の代理として請求をする場合に、被害者本人の意に状が必要となります。また、委任された者の印鑑登録証明書も必要です。
これらの書類を作成、用意をするのに、費用がかかる場合があります。この費用も領収書があれば、請求することができますので、必ず発行してもらい、請求書類と一緒に自賠責保険会社へ送るようにしましょう。
被害者請求したほうが良い場合とは?
a 任意保険に加入していない場合
自動車を運転する人の多くは、任意保険に加入をしていますが、加入していないケースも少なくありません。加入していない場合、経済的に余裕がないことが予想されます。もし、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者の自賠責保険へ直接被害者請求する方が良いでしょう。
加害者請求という方法もありますが、これは加害者が被害者に賠償をした後であることが前提になります。任意保険に加入していない加害者であれば、損害賠償をしない可能性が高いので、確実に損害賠償を一定額受け取るためにも、被害者請求をおすすめします。
b 示談が長引く場合
被害者は、加害者が加入している任意保険会社と示談交渉をすることがほとんどです。損害賠償金は示談が成立してから、一括で保険会社から被害者へ支払われますが、示談交渉が長引く場合、いつまでたっても被害者は受け取ることができません。こういったケースでも、加害者が加入している自賠責保険へ被害者請求すると良いでしょう。
c 被害者の過失割合が大きい場合
被害者の過失割合が大きい場合、加害者から受け取る予定の損害賠償金から過失相殺により、大きく減額される可能性があります。この場合、加害者に加入している自賠責保険に被害者請求をした方が、被害者が受け取れる金額が多くなることがあります。何故なら、自賠責保険は、被害者側が7割未満の過失の場合は、減額がなされないからです。
なお、過失相殺とは、被害者にも過失がある場合、被害者の過失割合分を損害賠償金より差し引かれることをいいます。
被害者請求の注意点
a 被害者請求の時効
被害者請求をするうえで気を付けなければいけないのは、交通事故の被害者請求には時効があることです。以下が時効起算点と期間です。
・事故発生日の翌日から3年以内
・死亡事故の場合は、死亡した日の翌日から3年以内
・後遺障害の場合は、症状固定をした日の翌日から3年以上
注意をしなければならないことは、令和2年4月1日より、民放が改正されたことにより、人の生命または身体の障害に関する損害賠償請求権利の時効は、5年となりました。しかし、自動車損害賠償保障法は、改正されておらず、時効は3年のままとなっています。
被害者請求をお考えの方は、大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイへ。
被害者請求についてご説明をいたしましたが、いかがでしたでしょうか?被害者請求は、時間と手間、さらには費用もかかります。被害者の負担が大きくなることから、被害者自身が途中で諦めてしまうこともあります。それでは、被害者にとって大きな損失となります。そうなってしまう前に、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士に依頼をすれば、被害者の方の代わりに被害者請求の手続きは行ってくれますので、被害者の方の負担は大きく軽減されます。
また、事案によっては被害者請求で補いきれなかった被害者の方の損害を、加害者側に請求することも可能な場合があります。
「被害者請求をしたい、でもやり方がわからない…」
「手続きが不安…」
このように被害者請求についてご不安がある方は、まずは一度、交通事故を多く取り扱う大阪市・難波(なんば)・堺市の弁護士法人法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談ください。

 06-4394-7790
06-4394-7790 お問い合わせ
お問い合わせ